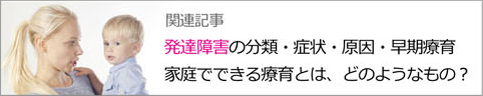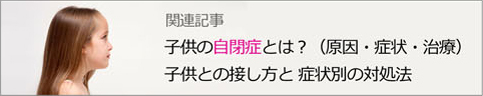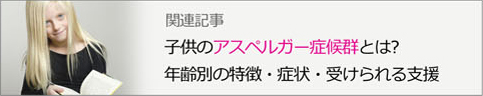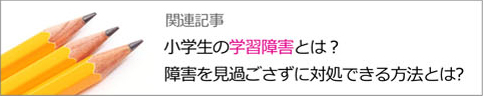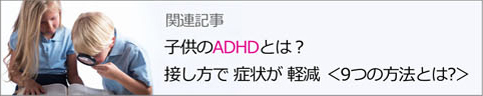発達障害と脳③〜脳の機能分化
2018-03-19 更新

はじめに
発達障害の子供に見られる症状として、手足を思うように動かせない、ボタンを上手にかけられない、靴ひもがきちんと結べないなどがあります。日常的な動作に問題が生じるため、強いコンプレックスに繋がる症状だと言えます。
ここでは、なぜ手足のコントロールが上手にできないのか、改善策はないのかをご紹介します。子供の発達の遅れに不安を感じている方は、ぜひ目を通してみてください。

複雑な動きを可能にするのは大脳の働き
私たちは大脳新皮質の働きによって身体を自由に動かすことができます。産まれたばかりの赤ちゃんは、大脳新皮質が未発達であり、身体を上手にコントロールすることができません。発達に応じて身体の各箇所に適切に命令を送るべく、脳の領域ごとに役割が分かれていきます。これは、「機能分化」と呼ばれる現象であり、脳の機能分化が進めば進むほど、高度で難しい動きができるようになると考えられています。
例えば、赤ちゃんは手足を別々に動かすことができないために、はいはいをして移動します。大脳新皮質の発達に伴って「右足だけを動かしなさい」、「左手だけを動かしなさい」など命令を送ることができるようになり、二足歩行が可能になるのです。
発達障害は脳の機能分化が不十分な状態
発達障害の子供は、脳の機能分化がうまく進まないまま成長してしまいます。どの領域の分化が不十分かによってあらわれる症状は異なりますが、代表的なものは以下の通りです。
- 手と口の未分化:ものを食べるときに手を口に入れ、押し込みながら食べる
- 手と足の未分化:手をつないだ状態で上手くバランスをとれない
- 目と体の未分化:目に入ったものにすぐに突進してしまう
- 左右の未分化:ボタンをしめるなど、両手を必要とする動作が上手くいかない。利き手が定まらない
分化には順番が決まっており、大きいところから小さいところへと進みます。「手と口」からはじまり、「手と足」、「目と体」、「左右」の順に分化していくのが一般的です。そのため、手を自在に使えるようにするためには、手足や口などの分化を進める必要があります。
そのため、発達障害の子供のトレーニングは、正しい手順で段階的に行わなければなりません。いきなり上位の問題に取り組んでも、改善が見込めないだけでなく、本人の自信とやる気をそぐ結果となってしまいます。
脳の機能分化を促す正しいトレーニング例
手と足の分化が不十分である場合の改善策として、歩行トレーニングが考えられます。手をつないで歩行することで、「足は歩く」、「手はつなぐ」という別々の動きを練習します。
目と身体の分化が不十分な場合は、座ったままDVDなどを見る着席注視トレーニングが有効です。
トレーニングを行う際のポイントとしては、分かりやすく目標を説明し、達成した時にはきちんと褒めてあげることを意識してください。できなかったことを叱るのでなく、ほんの少しでもいいので進歩した部分を探し、肯定的に見守る気持ちが成功を後押しします。
スピードは遅くとも、一歩一歩着実に成長する子供の姿を見れば、ご両親の意欲も高まるでしょう。トレーニングが思うように進まないこともありますが、前向きに焦らずゆっくり取り組んでください。
コラムメニュー
 発達障害の特徴
発達障害の特徴 発達障害の原因
発達障害の原因 発達障害は遺伝するの?
発達障害は遺伝するの? 発達検査の方法や診断結果
発達検査の方法や診断結果 自閉症の特徴
自閉症の特徴 自閉症への対応と治療方法
自閉症への対応と治療方法 アスペルガー症候群の特徴
アスペルガー症候群の特徴 アスペルガー症候群への対応と治療
アスペルガー症候群への対応と治療 多動性障害ADHDの特徴
多動性障害ADHDの特徴 多動性障害ADHDへの対応と治療
多動性障害ADHDへの対応と治療 学習障害(LD)の特徴
学習障害(LD)の特徴 学習障害(LD)への対応と治療方法
学習障害(LD)への対応と治療方法 発達障害の療育の種類と内容
発達障害の療育の種類と内容 発達障害の家庭療育のメリット
発達障害の家庭療育のメリット 発達障害の支援のポイントまとめ
発達障害の支援のポイントまとめ 発達障害から起こる二次障害
発達障害から起こる二次障害 障害者手帳の取得について
障害者手帳の取得について 発達障害児の進路
発達障害児の進路 発達障害児の就学先決定までの流れ
発達障害児の就学先決定までの流れ 言葉の遅れへの療育のポイント
言葉の遅れへの療育のポイント 発達障害と感覚の問題
発達障害と感覚の問題 発達障害とワーキングメモリー
発達障害とワーキングメモリー 発達障害と自己肯定感
発達障害と自己肯定感 ペアレントトレーニングとは
ペアレントトレーニングとは
発達障害と脳
 脳機能の障害とは?
脳機能の障害とは? 原始反射の残存
原始反射の残存 脳の機能分化
脳の機能分化 脳のコントロール機能の持続法
脳のコントロール機能の持続法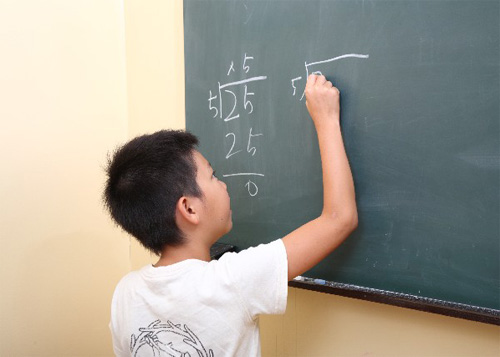 脳の混線状態
脳の混線状態 感覚統合あそび
感覚統合あそび