発達障害の支援のポイントまとめ
2018-03-19 更新

はじめに
注意欠陥多動性障害(ADHD)や学習障害、アスペルガー症候群など、発達障害の認知が広まったことで、「発達障害=個性」という考えが浸透しつつあります。周りの人たちが発達障害を抱える子供たちを正しく理解し支援することで、その子供たちはより安心して社会にとけ込むことができるのです。ここでは、発達障害を抱える子供たちへの支援のポイントを詳しく説明していきます。

具体的にお手本を見せる
何かに取り組むときや、子供に正しい行動を促すときには、言葉による説明だけではなく、絵に書いたり、やるべき行動をチェックリストにしたりというように、指示を具体化することが大切です。発達障害の子供たちは、視覚からの情報の方が理解しやすいため、より具体的なお手本を示すようにしましょう。例えば朝起きてから学校へ行くまでの支度の手順など、日常生活に欠かせない動作がなかなか覚えられない場合には、写真や絵を使ったカードを作成して動作の順番を伝えることも効果的な方法のひとつです。
また、説明や指示の仕方にもちょっとした工夫が必要です。発達障害の子供の多くは、曖昧な表現を理解することが苦手です。例えば、廊下を走っていた子供に対して「走っちゃダメ!」と注意をすると、その子供は走るのをやめて次はどうしたらいいのか困ってしまいます。この場合は「ゆっくり歩いてね」というように、正しい動作を具体的に伝えることが効果的なのです。時間の長さを表す「ちょっと」という言葉も同じで、「ちょっと」がどれくらいの時間なのか判断することができません。2分なのか3分なのか、具体的な数字を出して伝えることが理解の手助けとなるわけです。
「初めて」の体験で慌てさせない
発達障害の子供たちは、初めての場所や初めての出来事に対して不安を感じることが多いと言われています。これから起こることを予想したり、先の見通しを立てたりといったことが苦手な子供たちには、あらかじめこれから起こることや初めて行く場所についての説明をしておくことが大切です。初めて行くその場所には何があるのか、どのようなことが起こりうるのかを、事前に説明しておくことで、子供たちはパニックにならず安心して行動することができるのです。
叱らず上手に褒める
発達障害の子供たちにとって、成功体験の積み重ねは大きな意味のあることです。周りの子供たちが上手くできることが出来なかったり、倍の時間がかかってしまったりという経験を繰り返すうちに、自己肯定感が低く、劣等感を募らせてしまっている発達障害の子供たちは少なくありません。どんな些細なことでも出来たことを見逃さず、上手にほめることで、子供たちの自信へと繋げます。褒める際のポイントとしては、
- 良いことに気づいたらその場で褒める
- 必ず相手の目を見ながら、喜びや嬉しさをストレートに表現して褒める
- シールを貼るなどして成果を分かりやすくする
といったことが大切です。
では、どうしても許容できない行動が見られた場合にはどうしたらいいのでしょうか。まずは、その行動から目をそらし、注目をしていないことを態度で子供に知らせます。しばらく見守り、子供が問題行動をやめ、正しい行動をし始めたら、すかさず褒めます。万が一危険な行為などが見られた場合には、「やめなさい!」「何回言われたらわかるの!」というような曖昧な注意の仕方ではなく、「○○することをやめなさい」というように具体的に指示を出すようにします。この際、決して感情的にならず、穏やかに静かな声で注意をすることが大切です。
コラムメニュー
 発達障害の特徴
発達障害の特徴 発達障害の原因
発達障害の原因 発達障害は遺伝するの?
発達障害は遺伝するの? 発達検査の方法や診断結果
発達検査の方法や診断結果 自閉症の特徴
自閉症の特徴 自閉症への対応と治療方法
自閉症への対応と治療方法 アスペルガー症候群の特徴
アスペルガー症候群の特徴 アスペルガー症候群への対応と治療
アスペルガー症候群への対応と治療 多動性障害ADHDの特徴
多動性障害ADHDの特徴 多動性障害ADHDへの対応と治療
多動性障害ADHDへの対応と治療 学習障害(LD)の特徴
学習障害(LD)の特徴 学習障害(LD)への対応と治療方法
学習障害(LD)への対応と治療方法 発達障害の療育の種類と内容
発達障害の療育の種類と内容 発達障害の家庭療育のメリット
発達障害の家庭療育のメリット 発達障害の支援のポイントまとめ
発達障害の支援のポイントまとめ 発達障害から起こる二次障害
発達障害から起こる二次障害 障害者手帳の取得について
障害者手帳の取得について 発達障害児の進路
発達障害児の進路 発達障害児の就学先決定までの流れ
発達障害児の就学先決定までの流れ 言葉の遅れへの療育のポイント
言葉の遅れへの療育のポイント 発達障害と感覚の問題
発達障害と感覚の問題 発達障害とワーキングメモリー
発達障害とワーキングメモリー 発達障害と自己肯定感
発達障害と自己肯定感 ペアレントトレーニングとは
ペアレントトレーニングとは
発達障害と脳







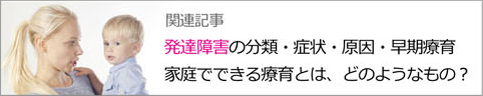
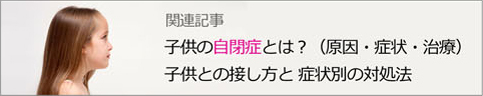
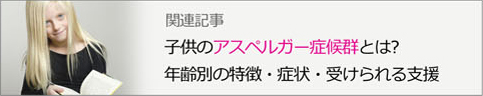
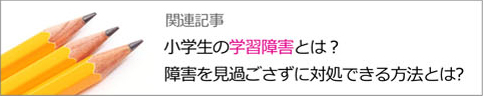
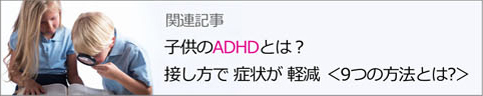
 脳機能の障害とは?
脳機能の障害とは? 原始反射の残存
原始反射の残存 脳の機能分化
脳の機能分化 脳のコントロール機能の持続法
脳のコントロール機能の持続法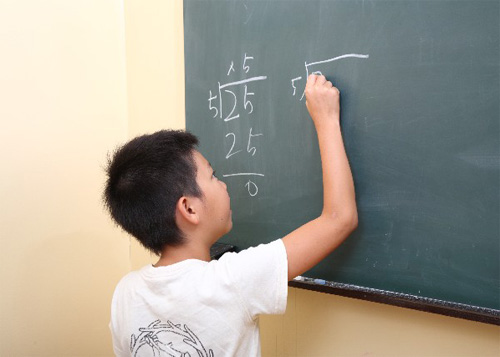 脳の混線状態
脳の混線状態 感覚統合あそび
感覚統合あそび